自然数nの分割 – 他の記事の補足説明 【飛ばしていた内容を補完】
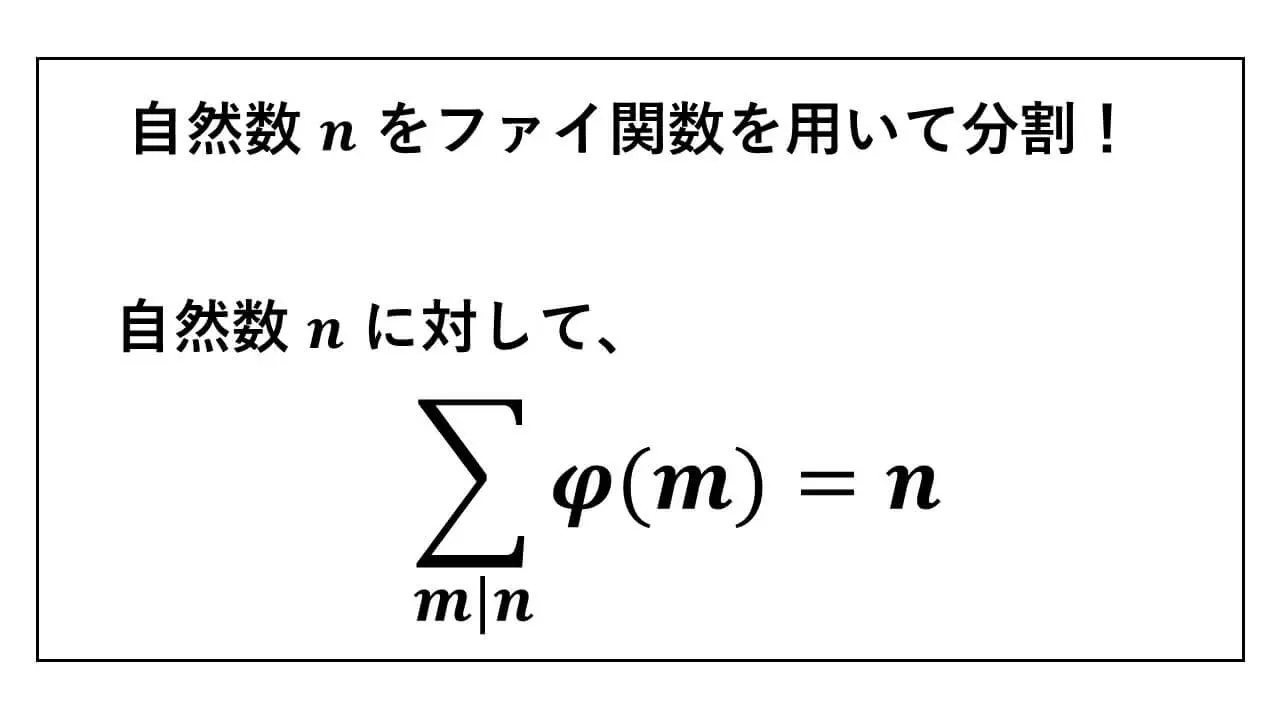
" 自然数nの分解 “について、初等整数論の有名な関数を用いた内容で示しています。
正確に証明をすると長くなりますが、途中の内容をしっかりと説明します。
【よく使う知識】
自然数 x と y の最大公約数を d としたとき、
x/d と y/d の最大公約数が 1 である。
この内容は、証明の中で使います。
自然数nの分割 :証明
【基本的な性質】
自然数 n に対して、
∑m|n φ(m) = n となる。
ただし、m は n のすべての正の約数を走る。
n = 1 のときは、φ(1) = 1 で成立するので、以下、n は 2 以上とします。
※ この φ はファイ関数です。
<証明>
n を 2 以上の自然数とし、n の 2 以上のすべての正の約数を k1, … , kt とします。
A = (Z/k1Z)×∪…∪(Z/ktZ)×,
B = {1, 2, … , n - 1}
A は各剰余環の元である集合たちをすべて集めた集まりです。
【f : A → B の定義】
x + kiZ ∈ (Z/kiZ)× (ただし自然数 i は 1 以上 t 以下で、1 ≦ x ≦ ki - 1) に対して、n/ki = n ÷ ki は n の正の約数です。
f(x + kiZ) = (n/ki)x と定義します。
※ (Z/kiZ)× の代表元を 1 以上 ki - 1 以下の整数に固定した、代表元の取り方に依存する写像です。
n/ki と x は n の正の約数なので、
(n/ki)x は正の整数となります。
1 ≦ x ≦ ki - 1 より、
(n/ki)x ≦ (n/ki)(ki - 1)
< (n/ki)ki = n
1 ≦ (n/ki)x ≦ n - 1 より、
f(x + kiZ) = (n/ki)x ∈ B
【g : B → A の定義】
y ∈ B に対して、n と y の最大公約数を y’ とします。
n/y’ を法として、
g(y) = (y/y’) + (n/y’)Z ∈ Z/(n/y’)Z と定義します。
1 ≦ y ≦ n - 1 なので、
n ÷ (n/y’) = y’ となり、y’ は正の整数より、n/y’ は n の正の約数です。
※ 1 = n/n < n/(n - 1) ≦ n/y’ なので、n/y’ は 2 以上の n の正の約数。
そのため、k1 から kt のどれかとなっています。
y/y’ と n/y’ は正の整数であり、
最大公約数が 1
そのため、
(y/y’) + (n/y’)Z は乗法逆元をもつので、
(Z/(n/y’)Z)× の元です。
そして、1 ≦ y < n より、
1 ≦ y/y’ < n/y’
つまり、1 ≦ y/y’ ≦ n/y’ - 1 なので、固定している代表元の値となっています。
したがって、
g(y) = (y/y’) + (n/y’)Z
∈ Z/(n/y’)Z ⊂ A
【 f が全単射である理由】
まず、gf が恒等写像であることを示します。
x + kiZ ∈ (Z/kiZ)× (ただし自然数 i は 1 以上 m 以下で、1 ≦ x ≦ ki - 1) に対して、
(gf)(x + kiZ)
= g(f(x + kiZ)) = g((n/ki)x)
(n/ki)x と n の最大公約数は n/ki となります。
※ この理由は後で示します。
g の定義から n/(n/ki) = ki を法として、(n/ki)x/(n/ki) = x を代表元とする値を対応させます。
そのため、g((n/ki)x) = x + kiZ です。
よって、(gf)(x + kiZ) = x + kiZ となります。
したがって、gf は恒等写像となります。
fg が恒等写像となることも後で示します。
以上より、gf と fg がともに恒等写像なので、f は全単射です。
したがって、
A に含まれる元の個数が、
B に含まれる元の個数 (n - 1) に一致。
A に含まれる元の個数は、
φ(k1) + … + φ(kt) なので、
φ(k1) + … + φ(kt) = n - 1
φ(1) = 1 を辺々足すと、
φ(1) + φ(k1) + … + φ(kt) = n
左辺は n の正の約数すべての和なので、結論が導けました。【証明完了】
飛ばしていた内容1
(n/ki)x と n の最大公約数 d は
n/ki となることを示します。
(n/ki) | (n/ki)x,
(n/ki) | n より
n/ki は (n/ki)x と n の公約数なので、
n/ki ≦ d です。
また、
公約数は最大公約数の約数より、
ある整数 p が存在し、
d = (n/ki) × p = np/ki と表せます。
d | n より、
(np/ki) | n です。
よって、
n÷(np/ki) は整数値です。
つまり、
n÷(np/ki) = ki/p は整数です。
このため、p は ki の正の約数です。
さらに、
d | (n/ki)x, np/ki | d より、
(n/ki)x÷(np/ki) は整数です。
約分をすると、
x/p は整数ということになります。
つまり、p は x の正の約数です。
以上より、p は x と ki の公約数です。
一方、
x+kiZ ∈ (Z/kiZ)×より、
x と ki の最大公約数は 1 です。
これより、p = 1 だから、
d = np/ki = n/ki 【証明完了】
もう1つ飛ばした内容を示します。
飛ばしていた内容2
fg が恒等写像となることを示します。
<証明>
y ∈ B とし、y と n の最大公約数を y’ とします。
(fg)(y) = f((y/y’) + (n/y’)Z) です。
n/(n/y’) = y’ より、f の定義から、
f((y/y’) + (n/y’)Z)
= y'(y/y’) = y
よって、(fg)(y) = y となり、
fg は恒等写像。【証明完了】
これで、自然数nの分割の内容です。
有限体-標数という記事でも飛ばしていた内容がありました。
ここからは、それを示しています。
他の記事の証明1
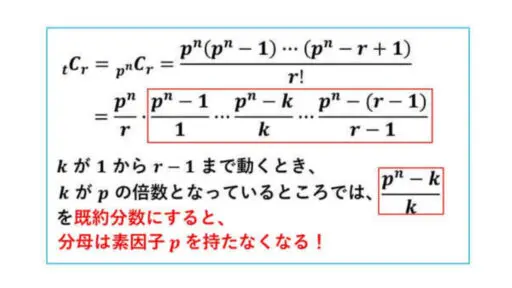
2 ≦ r ≦ t - 2 のときにも、p で割り切れることを証明します。
表紙の図のように k が走ります。
このとき、左辺が p で割り切れることを示します。
約分をすると左辺は整数値になるのですが、p を素因子として持っているのかどうかを確認する内容になります。
表紙の図の赤色で囲った部分で、分母を素因数分解したときに、素因子 p が現れるときは、k が p の倍数となっているところです。
そのとき、分子にも同じ k が使われています。
k を素因数分解したときの素因子 p の指数が pes だとします。
つまり、
k= pesa (a は自然数で a と p の最大公約数は 1) として、分子と分母を既約分数にすることを考えます。
ただし、
1 ≦ k < r < pn-2 という状況なので、
es < n です。
このとき、
(pn-k)/k
= (pn-pesa)/pesa
= (pn-es -a)/a
a と p の最大公約数は 1 なので、既約分数にすると分母は p を素因子としてもちません。
k が p の倍数でないときには、
(pn - k)/k を既約分数にしようが、しまいが、分母は p を素因子にもちません。
以上より、k が p を素因子に持つか、持たないかに場合分けされ、いずれの場合についても、
(pn - k)/k を既約分数にすると、分母は素因子 p を持たないということが示せました。
よって、表紙の図の大きく赤色で囲っている部分を既約分数にすると、分母は素因子 p を持たないということが示せました。
一番左の r ですが、r < pn なので、r が素因子 p をもっていたとしても、
その指数は最大で、
n-1 までです。
よって、pn/r を既約分数にしたときに、分子は素因子 p をもち、その指数は 1 以上ということが分かりました。
これで、tCr の公式を既約分数にしたときに、分子は素因子 p をもつということが示されました。
素因子として p をもっているのかどうかについての議論でしたが、高校で学習した整数の知識で考察を進めることで、結論に辿り着けるないようになっていました。
ここまでが、有限体-標数という記事の内容の補足説明になります。
次の段落では、テンソル積という記事で残していた証明の内容を述べます。
ユニバーサリティーについての内容となります。
他の記事の証明2
π’ : M × N → T’ について、
②の G として T を考え、
②の f として π を考えると、
π* : T’ → T が存在し、
π* ・π’ = π
一方、π : M × N → T について、
【定理】の G として T’ を考え、
【定理】の f として π’ を考えると、
(π’)* : T → T’ が存在して、
(π’)*・π = π’ となります。
よって、任意の (x, y) ∈ M × N に対して、
π*・(π’)*・π((x, y))
= π*・π'((x, y)) = π((x, y)) …(a)
これは、【定理】において、G として T、f として π を考えたものです。
ここで、T から T への恒等写像は Z-準同型写像で、それを id(T) と表すと、【定理】のおける G として T を、f として π を考え、
id(T)・π((x, y)) = π((x, y)) …(b)
(a) と (b) から、【定理】の Z-準同型写像が、ただ一つ存在するということから、
π*・(π’)* = id(T) です。
さらに、②の G として T’、
f として π’ を考えると、
(π’)*・π*・π'(x, y)
= π'(x, y) … (c)
ここで、T’ から T’ への恒等写像を id(T’) と表すと、
id(T’)・π'(x, y) = π'(x, y) … (d)
(c) と (d) から、②の Z-準同型写像が、ただ一つ存在するということから、
(π’)*・π* = id(T’) となります。
これで、π*・(π’)* = id(T) でもあったので、
(π’)* : T → T’ が全単射で、逆写像が π* ということになります。
よって、(π’)* は Z-加群としての同型写像なので、T と T’ が加群として同型です。【証明完了】
読んで頂き、ありがとうございました。